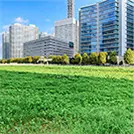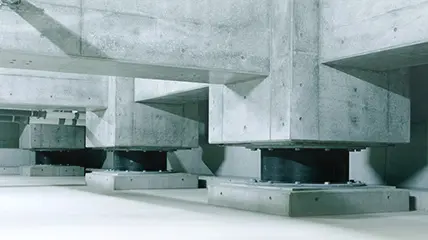相続の際、一定の金額以上の財産を受け取ると相続税をはじめとした税金が発生しますが、それらは対策をとることによって抑えることが可能です。 その手法の一つに「生前贈与」がありますが、今回は生命保険の非課税枠を活用したパターンを解説していきます。 生命保険を利用した節税対策は、保険料負担者や保険金受取人が誰かによってもメリットが異なるので、細かく確認していきましょう。
Point
- 生命保険金は相続税の対象
- 相続税における生命保険金の非課税枠は500万円
- 生命保険の内容によって税金の種類は異なる
-
目次
非課税枠を利用して相続税を抑える
被相続人が保険料を支払っていた生命保険や損害保険の保険金を、被相続人の死後に受け取る場合、相続財産としてみなされ課税対象となります。しかし、この保険金には非課税枠があり、うまく活用することで相続税対策が可能です。手法をチェックしていきましょう。
生命保険金の相続税における非課税枠は500万円
相続人が生命保険や損害保険の保険金を受け取った場合、相続財産として加算し相続税を払う必要がありますが、その際に500万円の非課税枠があります。つまり、500万円以内の保険金の受け取りには、相続税が発生しないということです。500万円以上の保険金であっても、相続税額において恩恵を受けることができます。
【難易度①】相続税の計算方法
仮に被相続人が父、相続人が子(一人のみ)とし、1億円を相続した場合の相続税を、生命保険金の受け取りがある場合とない場合で考えてみましょう。生命保険金の受け取りがあるケースでは2,000万円分を保険金と仮定します。
※葬儀代などの想定はなし。
※相続税には3,000万円+法定相続人一人あたり600万円の基礎控除があります。
※税率は国税庁「NO.4155相続税の税率」を参照しています。
生命保険金なしの場合
相続財産1億円に対する相続税を計算します。
- <課税遺産総額>
相続財産(1億円)-基礎控除(3,000万円+600万円)=6,400万円 - <相続税>
6,400万円×相続税率(30%)-控除額(700万円)=1,220万円
生命保険金ありの場合
相続財産8,000万円、生命保険金の受け取り2,000万円として相続税を計算します。
- <課税遺産総額>
相続財産8,000万円+生命保険金(2,000万円-非課税枠500万円)-基礎控除(3,000万円+600万円)=5,900万円 - <相続税>
5,900万円×相続税率(30%)-控除額(700万円)=1,070万円
このように、同じ金額を相続していても相続財産に生命保険金が含まれる場合とそうでない場合で、相続税に差がつきます。
紹介した例では生命保険金の非課税枠がポイントとなり、150万円の相続税が抑えられています。
【難易度②】非課税枠の分配
相続税における生命保険金の非課税枠500万円は「一人あたり」の金額なので、もし相続人が二人の場合は「500万円×二人=1,000万円」、3人なら「500万円×3人=1,500万円」が非課税枠となります。
それぞれの非課税枠
このとき、非課税枠は受け取る保険金の額で分配し、次の式で算出できます。
相続人ごとの非課税枠=
全体の非課税枠×その相続人が受け取る保険金の金額÷保険金総額
以下では、具体的な計算方法をご紹介します。
【例】
夫の死亡により2,000万円の生命保険金が発生し、妻と子二人で分配したとします。妻が1,000万円、子①が700万円、子②が300万円を受け取った場合、それぞれの非課税枠は以下のように計算します。
- 妻:1,500万円×1 ,000万円÷2,000万円
=750万円 - 子①:1,500万円×700万円÷2,000万円
=525万円 - 子②:1,500万円×300万円÷2,000万円
=225万円
それぞれの課税対象額
続いて、相続人それぞれの課税対象額を計算していきましょう。
課税対象額は、相続人ごとの非課税枠をもとに次の式で算出可能です。
相続人ごとの課税対象額=
その相続人が受け取る保険金の金額-相続人ごとの非課税枠
先ほどそれぞれの非課税枠を算出したので、その数字を使って課税対象額の具体的な計算方法を見ていきましょう。
- 妻: 1,000万円-750万円=250万円
- 子①:700万円-525万円=175万円
- 子②:300万円-225万円=75万円
非課税枠を活用することで課税対象額を減らすことができ、結果、相続税も抑えることができました。
こちらの例では、それぞれ4分の1にまで課税対象額を圧縮できています。
法定相続人以外にも相続できるメリットも
生命保険金の仕組みを活用すれば、法定相続人ではない方にも財産を残すことができます。
法定相続人以外の方に財産を残す方法には遺言を残す方法もありますが、保険金受取人にすれば、遺言の改ざんの心配や混乱などがなく財産を渡すことが可能です。
保険契約の内容によって課税される税金が異なる

被相続人を被保険者として、亡くなったときに保険金が受け取れるよう生命保険を契約した場合、課税される税金はケースにより異なるので注意が必要です。ここでは、夫を被相続人とした例で考えてみましょう。
| 保険料負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
|---|---|---|---|
| 夫(被相続人) | 夫(被相続人) | 妻や子(相続人) | 相続税 |
| 妻(相続人) | 夫(被相続人) | 妻(相続人) | 所得税 |
| 妻(相続人) | 夫(被相続人) | 子(相続人) | 贈与税 |
このように、保険料負担者と保険金受取人の関係により税金は異なります。
相続税の非課税枠を使い切ってしまっている場合などでは、生命保険金の税金を所得税で納めたほうが得になる場合もあるのがポイントです。保険金の受け取りは一時所得となり、所得税の計算時には保険金を得るためにかかった保険料を経費として差し引いて1/2をかけ、最大50万円の特別控除もあります。
ちなみに、被相続人が保険料負担者となり、法定相続人以外の方を保険金受取人として生命保険を契約した場合の相続税には、非課税枠は適用になりません。たとえば、被保険者が法定相続人ではない甥や姪を保険金受取人にした場合などです。
生命保険金の非課税枠で効果的な節税を
相続税を抑える手法の一つとして、生命保険金の非課税枠を活用する手法をご紹介しました。生前贈与の節税方法とあわせて、相続税対策にお役立てください。生命保険金の非課税枠を使い切っている場合は、保険料負担者を相続人にして生命保険を契約することで、所得税の対象にすることも可能です。自身にとってベストな方法を検討しましょう。
節税について詳しく知りたい方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
CONTACT
まずは気軽にご相談ください

- 相続の悩みを聞いてほしい!
- 土地活用について
相談したい! - 事業継承について
相談したい!
お電話でのご相談・
お問い合わせ
受付時間 10:00~17:00(水曜・日曜定休)