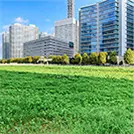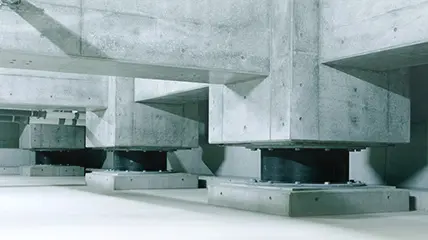相続税を計算するには、現金や預金、株式に限らず土地や建物などの価値も金銭で評価しなくてはなりません。 相続税計算の基準となるのが「相続税評価額」で、国税庁から公表されている「財産評価基準通達」にしたがって算出します。 この記事では、財産価値の基準となる相続税評価額について、土地と建物それぞれの計算方法について解説します。
Point
- 相続税評価額算出の基準となるのが「財産評価基準通達」
- 土地の相続税評価額の算出方法は「路線価方式」と「倍率方式」
- 建物の相続税評価額は賃貸中であれば30%減額される
土地の評価を知る方法
相続税の申告において、算出が難しいとされるのが「土地」です。
土地の相続税評価額を算出するには、「路線価方式」あるいは「倍率方式」を使用します。
路線価方式
主に都市部の住宅密集地、いわゆる市街地的形態を形成する地域に定められているものが路線価です。「路線価方式」とは、毎年国税局が作成する路線価図に基づき評価する方法で、土地の利用価値が高いと評価額が高くなります。
土地の利用価値に併せて、補正率・加算率が変わります。たとえば、二つの路線(道路)に面しているような利便性の高い角地は高評価で、土地の奥行や間口、地形などにより使いにくい場合は低評価になります。
評価方法は次のとおりです。
路線価×補正率・加算率×地積
倍率方式
「倍率方式」とは、都市郊外など路線価が定められていない地域で採用している方法で、地域ごとに定められた倍率に基づき評価します。算出には、固定資産税を算出するための基準となる「固定資産税評価額」を使用します。
評価方法は次のとおりです。
固定資産税評価額×倍率
建物の評価を知る方法

建物の相続税評価額は、固定資産税評価額の数字をそのまま使用するだけで算出できるため、土地の場合と比べてシンプルです。有償で賃貸している建物の場合は、自己利用や空き家と比較して30%評価額を減額できます。そのため、建物を賃貸中にしておくことで相続税の節税が可能です。
評価方法は次のとおりです。
自己利用家屋=固定資産税評価額
貸家=固定資産税評価額×70%
相続税評価額で土地や建物の価値が算出できる
相続税評価額を使用すれば、財産の価値を算出できます。土地や建物の相続で必要となりますが、とくに土地は算出に高い専門性が求められます。
相続税評価額について詳しく知りたい方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
CONTACT
まずは気軽にご相談ください

- 相続の悩みを聞いてほしい!
- 土地活用について
相談したい! - 事業継承について
相談したい!
お電話でのご相談・
お問い合わせ
受付時間 10:00~17:00(水曜・日曜定休)