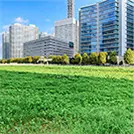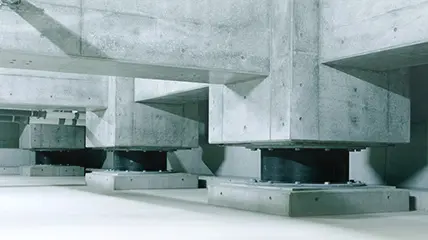相続登記は、2024年4月1日から義務化されました。今後は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。2024年4月1日より前に発生した相続についても義務化の対象となるため、すでに相続が発生している方も制度の内容を知っておくことが望ましいです。この記事では「相続登記の義務化」について解説します。
Point
- 2024年4月1日より相続登記が義務化される
- 2024年4月1日より前に発生した相続も義務化の対象となる
- 相続登記の期限は原則として、相続で取得したことを知った日から3年以内
-
目次
相続登記とは
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、不動産の所有権(名義)を被相続人から相続人へ変更する手続きのことです。
所有権の移転登記の理由(登記原因)には売買や贈与、相続などが存在しますが、相続を理由とした登記の名義変更のことを一般的に「相続登記」と呼んでいます。
相続登記の義務化の内容
相続登記の義務化の内容について解説します。
いつから義務化されるか
相続登記は、2024年4月1日以降から義務化されます。
義務化の制度自体は2024年4月1日以降に開始されますが、2024年4月1日より前に発生した相続も義務化の対象となります。
いつまでに相続登記が必要か
義務化された相続登記には、期限も設けられています。
相続登記をしなければならない期限は、以下の通りです。
▼2024年4月1日以降に相続が発生した場合
不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内
▼2024年4月1日より前に相続が発生している場合
以下のいずれか遅い日
・不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内
・2027年(令和9年)3月31日
不動産(土地・建物)を「相続で取得したことを知った日」とは、厳密にいうと「相続が発生した日」とは異なります。
相続では、たとえば死亡した被相続人に近い親族が次々と相続放棄をし、いつの間にか遠戚者の自分が相続人になってしまったというケースが考えられます。
近年は、資産価値のない空き家に相続が発生すると、このように近親者が次々と相続放棄をするケースがよくあります。 相続登記の期限は、このようにいつの間にか相続人になってしまったケースも想定しており、相続で取得したことを知った日から3年以内という表現になっているのです。
罰則はあるのか
正当な理由なく相続登記の義務を果たさない場合には、10万円以下の過料(かりょう)が課されます。
過料とは、金銭を徴収する制裁の一つです。 科料(かりょう)とは異なり、刑罰ではないことから、過料は課されても前科にはならいことになっています。
相続登記が義務化された背景
相続登記が義務化された背景は、所有者不明土地の発生を解消することにあります。
所有者不明土地とは、不動産登記簿などの所有者台帳により、所有者が直ちに判明しない、または判明しても所有者に連絡が付かない土地のことです。
所有者不明土地の主な発生原因は、相続登記がなされていないことにあります。
従来、相続登記をするかしないかは相続人の意思に任されていましたが、所有者不明土地が増えてしまったため、相続登記が義務化されるようになったのです。
相続登記に必要な書類
相続登記に必要な書類は、下表の通りです。
| 分割方法 | 必要書類 |
|---|---|
| 遺言による分割(※1) | ・遺言書 ・遺言者の死亡事項の記載のある除籍謄本 ・相続人または受遺者の現在の戸籍謄本 ・遺言により相続または受贈する相続人・受贈者の現在の住民票または戸籍の附票 ・固定資産評価証明書 |
| 遺産分割協議 による分割(※2) |
・遺産分割協議書(印鑑証明書付き) ・被相続人の10歳前後から死亡に至るまでの継続したすべての戸籍謄本など ・被相続人の除住民票または戸籍の附票 ・相続人全員の現在の戸籍謄本 ・遺産分割により相続する相続人の現在の住民票または戸籍の附票 ・固定資産評価証明書 |
| 法定相続 による分割(※3) |
・被相続人の10歳前後から死亡に至るまでの継続したすべての戸籍謄本など ・被相続人の除住民票または戸籍の附票 ・相続人全員の現在の戸籍謄本 ・被相続人の除住民票または戸籍の附票 ・固定資産評価証明書 |
出典:法務局 「不動産登記の申請書様式について」
※1:遺言とは、遺言者の生前の最終意思を尊重し、その意思の実現を死後に図る制度のことです。
※2:遺産分割協議とは、相続人同士で法定相続割合以外の割合で遺産を分ける話し合いのことを指します。
※3:法定相続とは、民法で定められた割合で共有することです。
相続登記の手続き
相続登記の手続きについて解説します。
2024年4月1日以前の相続の場合
2024年4月1日以前に相続が発生している場合、「遺言書がある」と「遺言書がない」で対処法が変わります。
遺言書がある場合は、2027年3月31日までに遺言書を用いて相続登記を行うことが必要です。 一方で、遺言書がない場合は、「遺産分割がまとまっている場合」と「遺産分割がまとまっていない場合」に分かれます。
遺産分割がまとまっている場合には、2027年3月31日までに遺産分割協議書(遺産分割協議の内容をまとめた書面)を用いて相続登記を行うことが必要です。
それに対して、遺産分割がまとまっていない場合には、とりあえず相続人申告登記(「第7章 相続登記ができないときの対処法」で詳述)を行っておくことが現実的な対処法です。
相続人申告登記も、2027年3月31日までに行う必要があります。
その後、遺産分割がまとまり次第、遺産分割の日から3年以内に相続登記をすることが必要です。
2024年4月1日以降の相続の場合
2024年4月1日以降に相続が発生している場合も、「遺言書がある」と「遺言書がない」で対処法が変わります。
遺言書がある場合、不動産を取得したことを知った日から3年以内に遺言書を用いて相続登記を行うことが必要です。 遺言書がない場合は、遺産分割がまとまっていれば不動産を取得したことを知った日から3年以内に遺産分割協議書を用いて相続登記を行います。
遺言書がなく、遺産分割もまとまっていない場合には、不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続人申告登記を行う必要があります。 その後、遺産分割がまとまり次第、遺産分割の日から3年以内に相続登記をすることが必要です。
登録免許税の免税措置

2025年3月31日までに行う相続登記において、一定の要件を満たす未了の相続登記では、部分的に登録免許税が課されない免税措置が存在します。
相続により土地の所有権を取得したものの、被相続人(死亡した人)が相続登記をする前に亡くなっているときは、被相続人へ所有権を移転する部分の登録免許税は免税となります。
たとえば祖父が死亡し、父も死亡しており、祖父と父との間の相続登記が未了の場合は、祖父と父との間の登録免許税は免税されるということです。
ただし、父と子の相続登記の登録免許税は課税されます。
詳しくは、法務局のホームページをご確認ください。
相続登記ができないときの対処法
遺産分割協議がまとまらず相続登記ができないときは、相続人申告登記をすることで過料を免れることができます。
相続人申告登記とは、暫定的に相続登記の義務を履行するための簡易な登記のことです。
相続人申告登記は、登記簿上の所有者が亡くなっていることをとりあえず公示する登記になります。 相続人申告登記は過料を免れることはできますが、相続登記ではないため、不動産を売却したり抵当権を設定したりするときには、相続登記をすることが必要です。
まとめ
以上、相続登記の義務化について解説してきました。
相続登記は2024年4月1日から義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。 2024年4月1日より前に発生した相続も、義務化の対象となります。
これから不動産の活用を検討している方や、相続登記でお困りの方は、下記お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
この記事のライター・監修者

不動産鑑定士
竹内英二
不動産鑑定事務所および宅地建物取引業者である(株)グロープロフィットの代表取締役。不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、住宅ローンアドバイザー、公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)、中小企業診断士。
土地活用と賃貸借の分野が得意。賃貸に関しては、貸主や借主からの相談を多く受けている。
竹内英二さんの記事一覧
CONTACT
まずは気軽にご相談ください

- 相続の悩みを聞いてほしい!
- 土地活用について
相談したい! - 事業継承について
相談したい!
お電話でのご相談・
お問い合わせ
受付時間 10:00~17:00(水曜・日曜定休)