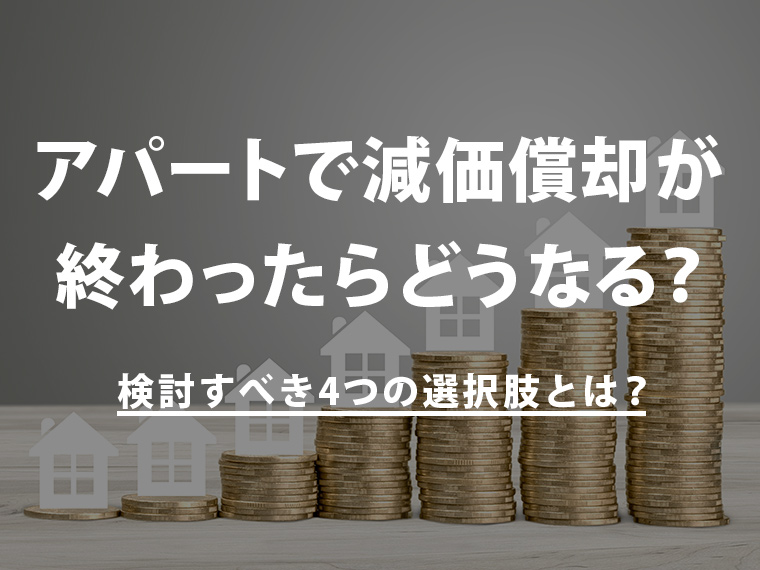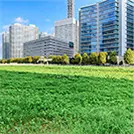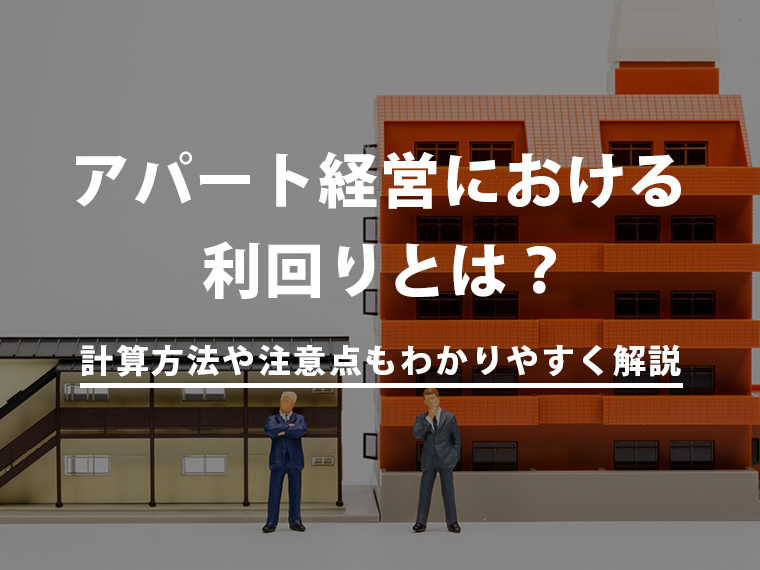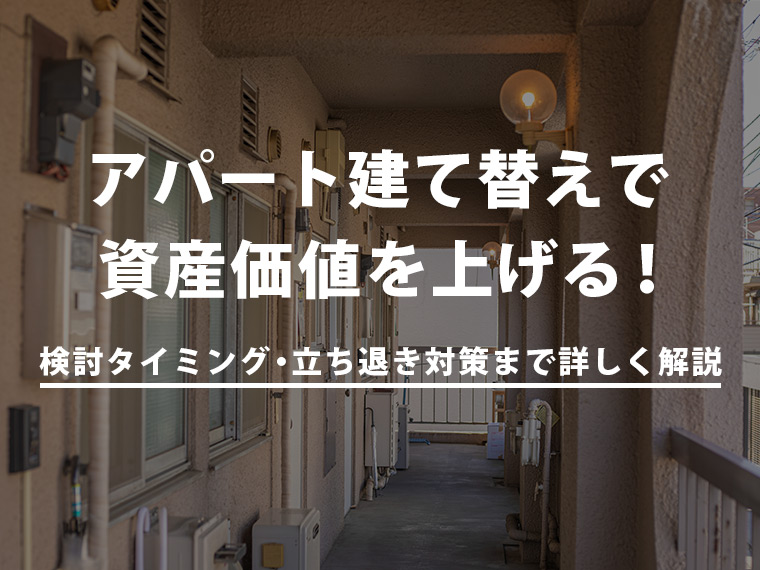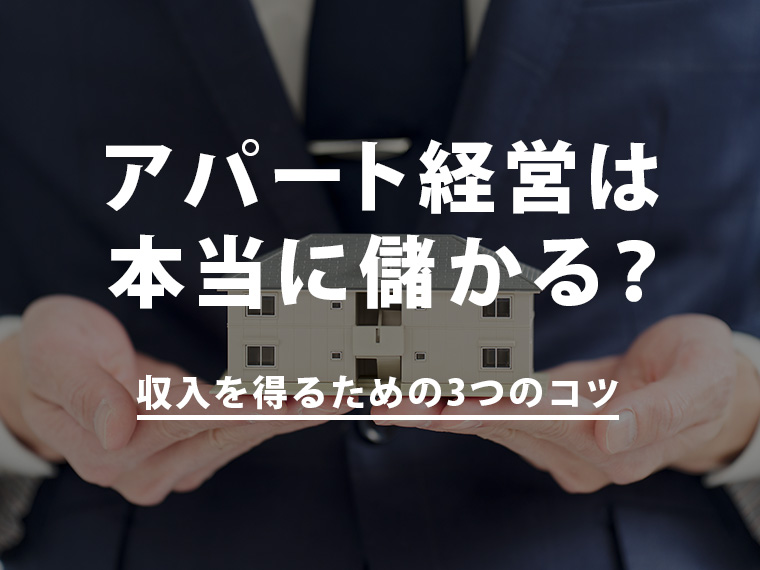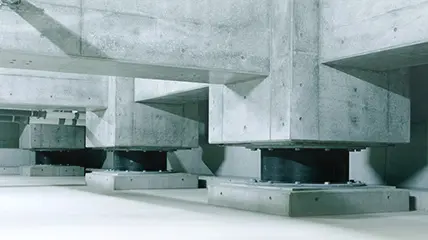賃貸経営の費用の中で、減価償却費は大きな割合を占める必要経費です。 この減価償却の計上が終わると、課税対象となる所得が増えるため、税金が一気に増えます。 さらに、減価償却が終わったタイミングで借入金の返済が残っていると、キャッシュフローにも大きな影響を及ぼしてしまいます。 では、アパート経営で減価償却が終わると、具体的にどのようなことが起こるのでしょうか。 この記事では、「アパートの減価償却が終わったらどうなるか」をテーマに解説します。
Point
- 減価償却が終わると所得税などの税金が増える
- 減価償却終了後に借入金が残っているとキャッシュフローが著しく悪化する
- 減価償却終了後には、継続運用やリノベーション、建て替えなどの選択肢がある
-
目次
減価償却とは?
減価償却とは、建物などの取得原価を耐用年数にわたって費用として配分し、その分だけ建物の簿価を減らしていく会計上の手続きのことです。 減価償却を行うことで生じる費用を「減価償却費」と呼びます。 減価償却費は、法定耐用年数の間、毎年計上される仕組みです。
法定耐用年数は建物の用途や構造によって定められており、アパートなどの賃貸住宅の法定耐用年数は下表のようになります。
| 構造 | 法定耐用年数 |
|---|---|
| 木造 | 22年 |
| 木造モルタル | 20年 |
| 鉄骨造(3mm以下) | 19年 |
| 鉄骨造(3mm超4mm以下) | 27年 |
| 鉄骨造(4mm超) | 34年 |
| 鉄筋コンクリート造 | 47年 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 47年 |
出典:国税庁 「主な減価償却資産の耐用年数表」
たとえば、木造アパートなら法定耐用年数は22年です。
新築で木造アパートを建てた場合、減価償却費を計上できるのは22年目までであり、23年目に入ると減価償却費の計上ができなくなります。
減価償却が終わったらどうなる?
この章では、減価償却が終了した後に生じる影響について解説します。
所得税などの税金が増える
減価償却が終わると、所得税や住民税などの負担が増加します。
個人でアパートなどの賃貸経営を行う場合、不動産所得に対して所得税や住民税が課税されます。 不動産所得とは、家賃収入から必要経費を差し引いた利益のことです。
不動産所得の求め方を示すと、以下のようになります。
不動産所得 = 総収入金額 - 必要経費
上式の「必要経費」の中には、減価償却費も含まれます。
アパート経営においては、一般的に減価償却費が最も大きな必要経費となっており、減価償却費が無くなることで不動産所得が一気に増えてしまうことが通常です。
所得税などは不動産所得に対して課税されるため、不動産所得の増加に伴って税金も増える仕組みです。
一見すると利益(不動産所得)が増えることは良いことのように思えますが、減価償却が終わっても家賃収入自体が増えるわけではありません。 家賃収入は変わらないのに税金だけが増えるため、減価償却が終わることは貸し主にとって、デメリットとなることが一般的です。
耐用年数でローンを組んでいたら返済はなくなる
多くの銀行が、新築時に組めるアパートローンの最長期間を「法定耐用年数」としています。
そのため、法定耐用年数に合わせてアパートローンを組んでいる場合、減価償却が終わると同時に借入金の返済も完了することになります。
減価償却が終わると税金は増えますが、借入金の返済も同時に終わる場合には、キャッシュフローへの影響は比較的小さく済み、ダメージは少ないです。
銀行が融資期間を法定耐用年数内に設定しているのも、法定耐用年数を超えて借入金の返済が残るとアパート経営が苦しくなる可能性を理解しているためです。
耐用年数超でローンを組むとキャッシュフローが急激に悪化する
中古アパートを購入した場合、アパートローンの融資期間が法定耐用年数を超えていることがあります。
この場合、減価償却が終わっても借入金の返済が残っているため、税金が増えることでキャッシュフロー(手残り)が一気に悪化してしまいます。
さらに、耐用年数を超えた不動産は築年数が古いため、家賃の下落や空室の増加、修繕費の発生など、収益を圧迫する原因が重なりやすくなります。 こうした状況で所得税などの税金まで増えてしまうため、アパート経営が急激に苦しくなってしまうのです。
減価償却が終わった後に検討すべき4つの選択肢

法定耐用年数を満了した築古アパートは、賃貸経営において一つの岐路に立たされます。
この章では、減価償却が終わった後に検討すべき選択肢について解説します。
①そのまま運用を続ける
新築でアパートを建て、法定耐用年数の満了と同時に借入金の返済も終えた場合は、そのまま運用を続けることをおすすめします。 理由としては、法定耐用年数を迎えても建物自体は十分使用できることが多く、借入金も完済していれば賃貸経営のリスクも大幅に下がるためです。
借入金の返済が無くなれば、たとえ税金が増えたとしてもキャッシュフローが改善されることが多く、今後は余裕を持った賃貸経営をすることができます。
②リノベーションを行う
減価償却が終わった物件は築年数が古いケースが多く、物件によっては空室が目立ち始めていることもあります。 空室が目立ち始めている場合には、空室対策としてリノベーションを行うことも選択の一つです。
空室対策リノベーションの具体例としては、和室を洋室に変更する、ベランダにある洗濯機置き場を室内に移すといった改修が挙げられます。
なお、空室対策はリノベーションに限りません。 たとえば、ペット飼育可物件とする、単身高齢者や外国人も入居可とするなど、入居者の条件を緩和することも有効です。
空室対策を行う場合には、管理会社とも十分に相談したうえで実施内容を決めることをおすすめします。
③建て替える
法定耐用年数を迎えても、建物自体はまだ使用できることが多いため、減価償却費が終わったからという理由ですぐに建て替えるのは早計です。 ただし、建て替えを行うには現在の入居者の立ち退きが必要となるため、建て替えは長期的な視点で計画することが望まれます。
たとえば、新規の入居者との契約を「定期借家契約(更新の概念のない契約)」に切り替えていけば、更新がなく契約満了で確実に退去してもらえるため、立ち退き料も不要になります。
このように、徐々に定期借家契約へ移行していくことで、将来スムーズに建て替えを実行できる体制を整えることが可能です。
④売却する
減価償却が終わった物件は、売却することも選択肢となります。 とくに、借入金の返済が残っている場合には、キャッシュフローが著しく悪化してしまうため、売却が効果的な対策です。
また、大規模修繕や建て替えに必要な資金を捻出できない場合も、売却を検討する価値があります。 築年数の古い物件は、今後さらに収益性が下がる可能性があるため、築年数の新しい物件に買い替えることも有効な判断です。
まとめ
以上、アパートの減価償却が終わった後の影響について解説してきました。
減価償却が終わると必要経費が減るため、所得税などの税金が上がります。 法定耐用年数に合わせてローンを組んでいれば借入金の返済は完了しますが、耐用年数を超えてローンを組んでいる場合は、キャッシュフローが急激に悪化する可能性があります。
減価償却が終わった後には、そのまま運用を続ける、リノベーションを行う、建て替える、売却するといった選択肢を検討することが重要です。
減価償却が終わった後の対策を検討している方は、下記よりお気軽にご相談ください。
この記事のライター・監修者

不動産鑑定士
竹内英二
不動産鑑定事務所および宅地建物取引業者である(株)グロープロフィットの代表取締役。不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、住宅ローンアドバイザー、公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)、中小企業診断士。
土地活用と賃貸借の分野が得意。賃貸に関しては、貸主や借主からの相談を多く受けている。
竹内英二さんの記事一覧
CONTACT
まずは気軽にご相談ください

- 相続の悩みを聞いてほしい!
- 土地活用について
相談したい! - 事業継承について
相談したい!
お電話でのご相談・
お問い合わせ
受付時間 10:00~17:00(水曜・日曜定休)